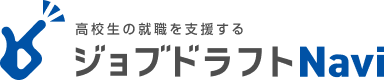【高校生向け】自動車免許の取得方法と注意点を紹介
高校生活も終盤に差し掛かり、就職など新しいステージへ向けて準備をしている人も多いでしょう。
その中で、自動車免許の取得を考えている人も少なくないはずです。
免許を持っていると通勤の幅が広がるだけでなく、選択する職種や仕事、趣味やアウトドア活動の幅も広がります。
ここでは、高校3年生向けに自動車免許の取得方法や流れ、注意点についてわかりやすく解説します。
1. 自動車免許の種類を知ろう
日本で一般的に取得される自動車免許は「普通自動車運転免許」です。
この免許があれば、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の普通車を運転できます。通学用や日常の移動でよく使われる車で必要な免許も普通自動車免許です。
【例】
・ 一般的な乗用車(普通自動車や軽自動車)
・小型トラック(2トン未満)
・原動機付自転車
・小型特殊自動車 (農耕用トラクターやフォークリフトなど)
普通自動車免許を取得するには、18歳に達していることが最低条件となります。
つまり、高校3年生で18歳の誕生日を迎えた人から取得することが可能です。多くの高校生はこの年齢を迎える12月以降に取得を目指すケースが多いでしょう。
2. 免許取得の基本的な流れ

自動車免許の取得は、「教習所(自動車学校)」での教習を受けて、卒業検定に合格した後、試験場での本免許試験に合格することで完了します。大まかな流れは次の通りです。
①入校手続き
まずは自動車教習所に入校します。入校には以下のものが必要になることが多いので事前に準備しましょう。
・住民票の写し
・保険証など身分確認ができるもの
・眼鏡/コンタクトレンズ(※視力が片眼で0.3及び両眼で0.7未満の場合)
教習所によっては視力検査などがあり、免許取得のための基準を満たしているかの事前チェックもあります。
②学科教習・実技教習
教習所では学科教習と実技教習の両方を受けます。学科は交通ルールや安全運転の知識を学ぶもので、一定時間の受講が義務づけられています。
実技教習は実際に車を運転する練習で、基本操作や路上走行、駐車などの技術を身につけます。こちらも一定時間の受講が義務付けられておりますが、時間の基準を満たしても、教習指導員から技能試験で合格判定がもらえなかった場合は延長となり、教習所によっては延長回数分の追加料金が必要となる場合があります。
③仮免許の取得
教習所の初期段階を終えて、仮免許試験(筆記試験)に合格すると、一定の条件付きで実際の道路上を運転できる「仮免許」が交付されます。
仮免許があると、教習所の指導員の同乗のもと、より実践的な路上教習が受けられます。
④卒業検定
全ての教習を終えた後、卒業検定という運転技能の試験を受けます。これに合格すると、教習所を卒業し、卒業証明書が発行されます。
⑤本免許試験(運転免許試験場で受験)
卒業証明書と必要書類(住民票の写しや身分証明書等)を持って運転免許試験場に行き、学科試験に合格すれば免許証が交付されます。
普通自動車免許の場合、公認の自動車学校を卒業した人は技能試験は免除されますが、非公認の自動車学校を卒業した場合は、学科試験に加え技能試験も受けることになります。
3. 合宿免許という選択肢
通常の通学型教習所の他に、短期間で集中して免許を取得できる「合宿免許」もあります。合宿免許とは、全国各地の教習所が実施する宿泊施設に泊まり込み、数日から数週間の集中教習を受けるスタイルのことです。
合宿免許のメリット
・短期間で免許が取得できる
通常の通学教習よりもスケジュールが詰まっているため、最短で2週間程度で免許を取得できる場合があります。夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用して効率的に取得したい人に向いています。
・費用が比較的割安
入校から卒業までの教習料に加えて、宿泊費や食事代がセットになっていることが多く、別途かかる生活費を含めて考えた場合、通学よりも費用を抑えられるケースがあります。
・新しい仲間との出会い
同じ時期に免許取得を目指す仲間と生活を共にするため、励まし合ったり情報交換しながら教習を進められます。
合宿免許の注意点
・一定期間の拘束がある
合宿期間中は教習のスケジュールがタイトで、自由な時間が限られます。個人的な用事やアルバイトとの両立は難しいため、その点を理解しておく必要があります。
・地域を選ぶ必要がある
合宿免許は全国各地で行われています。地元だけでなく、遠方での教習を選ぶ場合は、移動費や帰省費用も考慮しましょう。
・学校との調整が必要
高校3年生の場合、長期休暇を活用するのが一般的ですが、休みの期間と合宿期間が合わない場合は学校との相談が必要です。
4. 免許取得にかかる期間と費用
教習所での所要時間や自分のスケジュールによって取得までの期間は変わりますが、最短で2ヶ月程度が目安です。自由登校期間に入る前から早めに取得を目指す高校生は、学校の授業や行事と両立しながら進めるため、3〜4ヶ月かけて取得する人もいます。
一方、合宿免許なら最短で約2週間で取得可能です。
費用については、教習所によって異なりますが、普通自動車免許の取得にかかる費用はおおむね30万~35万円が一般的です。合宿免許では、宿泊費や食事代が含まれているプランが多く、費用面で比較すると同程度か少し割安なケースが多いです。
5. 高校在学中の免許取得で注意すべきポイント

①年齢制限とタイミング
18歳にならないと普通自動車免許を取得できません。誕生日が2・3月の高校生は、誕生日の直後に入校するのが効率的です。特に合宿免許では参加開始日が決まっていることが多いため、計画的に申し込むことをおすすめします。
②教習所選び
通学型だけでなく合宿免許も選択肢に入れて、費用や期間、通いやすさを比較し、自分のライフスタイルに合った教習所を選びましょう。
教習所によっては送迎を行ってくれる場合もあります。
③学業との両立
通学教習の場合は学業と両立が求められます。
合宿免許の場合は短期間に集中して取得するため、学校行事や受験との兼ね合いを考慮するとよいでしょう。
場合によっては学校で免許取得を禁止していたり、一定の期間までは制限していることがあるので、気になる場合は学校の先生に相談してみましょう。
④就職先で必須となることも
企業によっては、就職時に普通免許の取得を必須条件としている場合があります。
求人票の「必要な知識・技能等」項目の確認をするか、不安であれば企業側に直接問い合わせてみましょう。
⑤安全意識の徹底
免許を取った後は自動車の運転が生活の一部になります。安全運転のための心構えを今のうちからしっかり身につけてください。初心者は特に事故のリスクが高いため、運転に慣れるまでは慎重に、スピードや周囲の状況に気を配ることが大切です。
また、普通自動車免許を取得する場合に必要な視力は、「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、または一眼の視力が0.3に満たない方、もしくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上」となります。
この視力は、裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトを着用した場合でも有効です。
眼鏡・コンタクト着用で基準を満たし免許を取得した場合、裸眼で運転すると罰則が課せられるので注意が必要です。
6. まとめ
高校3年生の皆さんにとって、自動車免許の取得は将来の選択肢を広げる大事なステップです。余裕を持って教習所に通い、計画的に学科・実技の教習を受けましょう。
通学型教習所のほか、短期間で免許が取れる合宿免許も検討し、自分の生活スタイルに合った方法を選んでください。
教習の合間にはしっかり休息と学業を両立し、無理のないペースで挑戦することが免許取得成功の秘訣です。また、免許取得後は安全運転の意識を持つことも忘れずに。これから免許取得を目指す皆さんの一歩が、安心で楽しいカーライフにつながることを願っています。