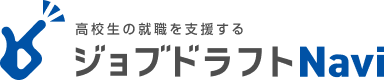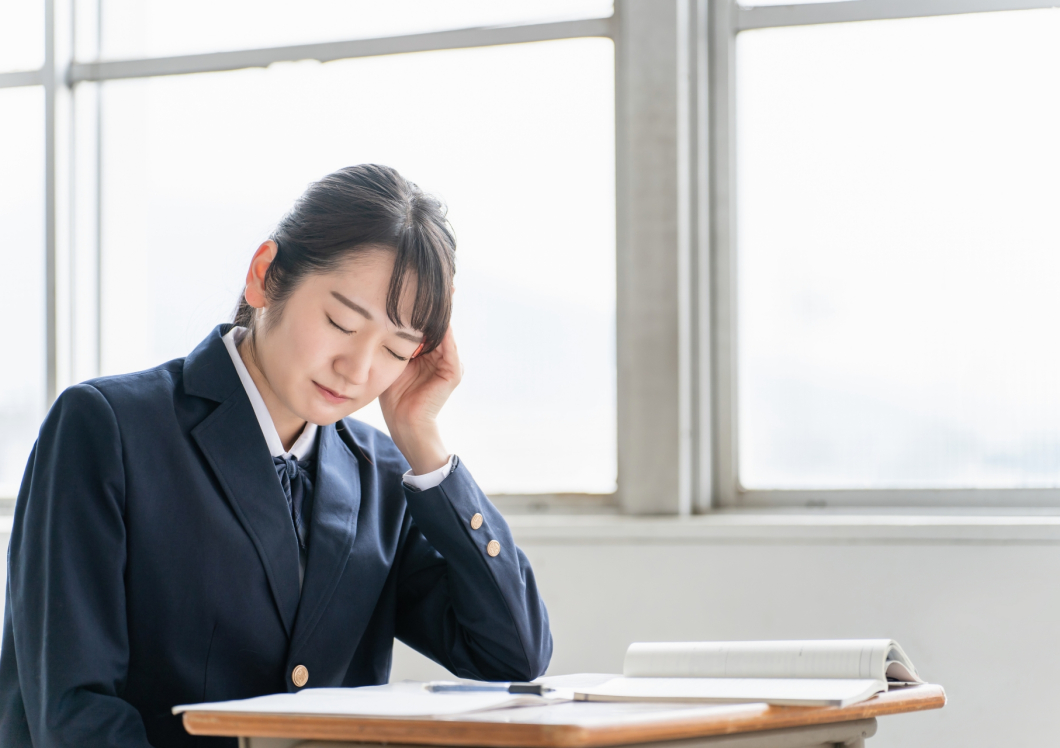
高校3年生、欠席が多いと卒業できない?知っておきたい「日数ルール」と注意ポイント
高校3年生になると、受験や進路の準備で忙しくなるだけに、「休んでいい日数」「あと何日休めるか」が気になる人も多いと思います。
しかし、「何日休むと卒業できないか」は、実は学校ごとにルールが違ったり、細かい条件があったりします。
今回の記事では、一般的な目安と、間違えやすいポイント、そして対策までを高校生向けにまとめました。
1.卒業に必要な条件とは?
高校を卒業するには、次の3つの条件を満たす必要があるとされています。 3年間(またはそれに相当する期間)在籍していること
74単位以上を修得していること
※通信高校は学校によっては60〜74単位ほどの場合あり
各教科・科目で出席日数などが基準を満たしていること
この3つの条件がそろってはじめて「卒業見込み」となるケースが多いです。
つまり「出席日数」は卒業に関係している大切な要素の一つになります。
2.出席・欠席のルール ― 一般的な基準とは?
●年間授業日数×1/3が目安(=約66日)
実は「◯日休んだら卒業できない」という全国共通のルールはありません。
高校ごとに細かい基準が違いますが、授業日数の3分の1以上を欠席すると危険ラインとされています。
目安としては――
1年間の授業日数が約200日ある場合
→66日以上欠席すると危険信号
ただし「66日休んだから即アウト」というわけではなく、実情はもっと複雑です。
●科目別に出席時間で判定される
重要なのは「学校全体での欠席日数」ではなく 各科目ごとの出席時間(出席時数) で基準を満たすかどうかを判断する高校が多いという点です。
たとえば、英語・数学・体育…といった各教科で、出席時間が基準に足りなければ、その科目の単位が落とされることがあります。
必修科目で単位を落とすと、進級できなくなったり、卒業できなかったりするリスクが高まります。
●遅刻・早退にも注意!
また、遅刻・早退も単位や進級に影響を与える「落とし穴」になりえます。
たとえば、ある授業の開始後すぐに遅刻を繰り返していると、「その授業をしっかり受けた」とみなされず、出席時間が不足になることがあります。
特定の曜日や特定の授業で遅刻・早退が集中すると、その科目で「時間が足りない」と判定される可能性もあります。
●高校によってルールが異なる
上記の「66日」「3分の1」などはあくまで 一般的な目安 です。実際には、
・学校によって欠席の基準(3分の1・4分の1など)
・必修科目・選択科目での違い
・出席停止や疾病・けがなどでの特例扱い
などの違いがあります。
もし、自分の通う高校のルールが気になる場合は、先生に尋ねてみましょう。
3.安心して卒業するためにできること
●担任・教科担当の先生に相談
「自分はあと何日休んだら危ないのか?」という質問を先生に聞くのが一番確実です。
特に、どの科目が危ないか、補習や救済措置が取れるかを教科担当の先生とも話しておきましょう。
●休んだ理由・証明をきちんと残す
病気・けが・検査入院など正当な理由がある場合は、 診断書などの証明書を残しておきましょう。
学校側が「出席停止扱い」にする場合もあります。
この場合、欠席日数にカウントされず、進級・卒業に影響しないこともあります。
●遅刻・早退をできるだけ減らす
授業開始ギリギリで毎回遅刻をしていたり、あるいは途中で早退というのは、出席時間が不利になる可能性があります。
可能な限り遅刻・早退をしないように心がけましょう。
●状況がどうしても厳しいときは別の選択肢も考える
もし、今の高校でどうしても進級・卒業が難しいなら、別の進路も検討できます。
たとえば通信制高校への転校など。実情に合ったサポートや登校の仕方が違う学校もあります。
4.まとめ
「何日休んだら卒業できなくなるか」は、一律には言えないルールです。
出席・欠席の目安は学校毎に違うので、気になる方は校長先生や県の教育委員会にお問い合わせください。
最も大切なのは、早いうちに先生に相談することです。
できるだけ状況を正確に把握して、最後まであきらめずに行動していきましょう。