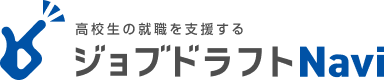高校就活成功の近道!求人票の見つけ方・活かし方ガイド
高校生の皆さん、こんにちは!就職活動は将来を左右する大切な一歩であり、その中でも「求人票」は皆さんの進路を決める上で最も重要な情報源となります。
自身である程度自由に行える大学生の就職活動とは異なり、高校生の就職活動には独自のルールや流れがあり、高校卒業までの限られた期間の中で、いかに効率的に求人票を見つけ活用できるかが、成功の鍵を握ります。
本記事では高校生の皆さんが希望の職に就けるよう、自分に合った求人票を見つけるための具体的な方法を詳しく解説します。
それぞれの方法のメリット・デメリット、そして活用する上でのポイントを理解し、皆さんの就職活動に役立ててください。
1.高校生の就職活動における求人票の探し方・見つけ方
高校生の就職活動では、主に以下の3つの方法で求人票を見つけることができます。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法や、複数の方法を組み合わせて活用してみましょう。
1. 学校に届いた求人票を活用する

高校生の就職活動において、最も一般的な方法が学校に届いた求人票を活用することです。
これは、企業が直接地域の高校に求人を出す「学校推薦」の形が一般的だからです。
【求人票が学校に届く仕組み】
企業は高校生の新卒採用の意欲がある場合、直接各高校に進路指導担当者宛に求人票を送付します。
また、ハローワーク(公共職業安定所)が企業から受け付けた求人のうち、特に「学校に紹介する求人」として高校に情報提供を行う場合もあります。
【閲覧方法】
多くの高校では、進路指導室に求人票がファイリングされていたり、掲示板に貼り出されたりしています。
進路指導の先生が、生徒の希望や適性に応じて個別に紹介してくれることもありますし、最近では各高校の就職情報に関するウェブサイトやSNSで案内されるケースも増えています。
【メリット】
- ・安心感と信頼性:学校が事前に求人内容を確認しているため、不当な労働条件の求人が少なく、安心して応募ができます。
- ・学校の手厚いサポート:進路指導の先生が応募書類の添削、面接指導、職場見学の申し込みを行うなど、手厚いサポートをしてくれます。
- ・学校推薦の有利性:企業からの信頼度が高く、選考において有利になる場合があります。
- ・地元優良企業との出会い:地域に根差した中小企業や、これまで多くの卒業生が就職してきた実績のある企業からの求人が多く、安定した職場を見つけやすい傾向があります。
- ・就活スケジュールの明確化:7月1日の求人票情報解禁日や、9月16日以降の選考開始など、毎年決まったスケジュールで行われるため、計画的に準備を進められます。
【デメリット】
- ・選択肢の限定:その学校に求人を出している企業に限られるため、選択肢が広範囲ではありません。
- ・情報解禁日までの待ち期間:応募開始まで、過去の求人票などを利用し情報収集に徹する必要がある期間が存在します。
- ・学校推薦の制約:複数の企業に応募できない、あるいは特定の条件を満たす必要があるなど、応募に制約がある場合があります。
【活用する上でのポイント】
進路指導の先生とは普段から密に連携を取り、自分の希望する職種や業界、学びたいことなどを具体的に伝えておきましょう。早めに情報収集を始め、過去の求人票やOB・OG情報を参考に、興味のある企業をリストアップしておくことも有効です。
夏休みなど長期の休み期間中に職場見学に積極的に参加し、企業への理解を深めることも、求人票を選定する上で非常に役立ちます。
2. 求人サイトを利用する
近年、インターネット上の求人情報サービス、いわゆる「求人サイト」を利用して就職活動を行う高校生が増加傾向にあります。
高校生向けに特化したサイトも登場しており、幅広い情報にアクセスできます。
【閲覧方法】
パソコンやスマートフォンから求人サイトにアクセスし、希望する業種・職種・勤務地・給与などの条件で検索を行います。 興味のある企業があれば詳細情報を閲覧し、職場見学の申し込みや応募をすることもできます。
【メリット】
- ・情報量の多さと多様性:全国各地の幅広い業種・職種の求人が掲載されており、選択肢が非常に広く、自分の希望に合った企業を見つけやすいです。
- ・24時間アクセス可能:自分の都合の良い時にいつでも求人情報を検索・閲覧できるため、学業や部活動と両立しながら就職活動を進められます。
- ・比較検討のしやすさ:複数の企業の情報を並べて比較検討しやすく、自分にとって最適な企業を見つけやすくなります。
- ・企業の雰囲気の把握:写真や動画で職場の雰囲気を紹介しているサイトも多く、実際に働くイメージがしやすいです。
- ・サポート性:求人サイトによっては、チャット等で個別に進路相談などを行ってくれる場合があります。
【デメリット】
- ・情報の信憑性:新規高卒者向けの求人票は全てハローワークのチェックが入っていますが、学校からのチェックはされているわけではないため、自分で内容を吟味し、不明な点があれば企業に直接確認するなど、慎重な対応が求められます。
- ・自己責任:学校の先生を通さない「自己開拓」での就活を行う場合、応募から選考、入社まで基本的には自己責任で進める部分が多くなります。
もちろん、学校の先生を通して行うこともできます。 - ・情報過多:情報が多すぎて、どれを選べば良いか迷ってしまうことがあります。
- ・学校のサポートが薄い:学校推薦制度のような手厚いサポートは期待できない場合が多いです。
【活用する上でのポイント】
高校生向けの求人情報に特化したサイトや、信頼性の高い大手求人サイトを選ぶようにしましょう。応募前には、必ず企業の公式ウェブサイトを確認し、企業情報を詳しく調べてみてください。
気になる求人票があればスクリーンショットを撮ったり印刷などを行い、後から見返せるように整理しておくことが重要です。インターネットで応募する場合でも、事前に進路指導の先生に相談しアドバイスをもらうことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
学校や求人サイトにない求人票を探す
上記2つの方法で見つからない場合でも、公共機関のサービスや、国が提供するシステムを通じて求人を探すことができます。 ただし、これらの方法は「学校の先生を通す」ことが原則となります。個人で自由に閲覧・応募できるわけではない点に注意しましょう。
ハローワーク(公共職業安定所)の活用

厚生労働省が運営する全国に設置された職業紹介機関です。企業からの求人票が日々集まり、求職者に情報が提供されています。
【高校生が利用する場合の注意点】
高校生は、基本的に学校を通してハローワークの求人情報を閲覧・応募します。個人で直接ハローワークの求人に応募することはできません。
進路指導の先生がハローワークの求人情報を収集し、生徒に紹介する形が一般的です。
【メリット】
- ・豊富な求人情報:地域の中小企業から大手企業まで、幅広い求人情報が集まっています。学校には直接求人を出していない企業の情報も得られる可能性があります。
- ・地域密着型:地元の求人が豊富で、Uターン・Iターン就職を考えている場合にも有効です。
【デメリット】
- ・学校を通す必要性:高校生がハローワークの求人情報を閲覧したり応募したりする際は、原則として学校の先生を介する必要があります。このため、個人の裁量で自由に情報収集や応募を進めることができず、情報伝達や手続きに時間を要する場合があります。
- ・情報更新の遅延:ハローワークに届いた最新の求人情報が、学校を通じて生徒の手元に届くまでにはタイムラグが生じる可能性があります。
人気の求人など、情報の鮮度が重要な場合には、この遅延が機会損失につながることも考えられます。 - ・求人の質にばらつき:学校に直接届く推薦求人と比較すると、ハローワークに掲載されている求人の中には、新規高卒者を育てる体制や福利厚生などが必ずしも十分に整っているとは限らない企業も含まれる可能性があります。
応募前には、より一層の企業情報確認が必要となる場合があります。
【活用する上でのポイント】
希望する地域のハローワークに、学校の先生がどのような形で情報収集しているかを確認しましょう。
先生と連携し、ハローワークの求人情報を積極的にチェックしてもらうよう依頼することで、より多くの選択肢に出会える可能性があります。
高卒就職情報WEB提供サービスの活用
文部科学省と厚生労働省が連携して提供する、高校生向けの求人情報サイトです。全国の高校新卒者向けの求人情報が掲載されています。
【高校生が利用する場合の注意点】
このサービスは、基本的に学校の先生のみがアクセスできるものになっています。 個人で自由に登録・閲覧できるわけではないため、サービスを活用したい場合は担当の先生に相談しましょう。また、応募も学校を通じて行います。
【メリット】
- ・全国の求人情報を検索可能:全国各地の高校生向け求人情報を閲覧できます。
- ・求人票の閲覧・印刷が容易:気になる求人票を画面上で確認し、印刷することも可能です。
- ・公共機関の信頼性:国が運営しているため、安心して利用できる情報源です。
【デメリット】
- ・学校所有のID・パスワードが必須:このサービスは、個人が自由に登録・アクセスできるものではなく、利用するためには学校や進路担当の先生が所有している専用のIDとパスワードが必要です。これにより、サービスを活用したい場合は担当の先生に相談する必要があります。
- ・応募は学校を介して行う:サービス上で求人票を閲覧することは可能ですが、実際の企業への応募手続きは、必ず学校を通じて行われます。生徒が自身のタイミングで企業に直接応募することはできないため、スピーディーな応募が難しい場合があります。
- ・直接的なサポートは提供されない:このサービスは、求人情報の検索と閲覧に特化しており、個別のキャリア相談・応募書類の添削・面接指導といった就職活動における手厚いサポートは提供していません。
これらのサポートは、学校の先生に依頼する必要があります。
【活用する上でのポイント】
進路指導の先生にサービスの利用について相談しましょう。 学校の先生と一緒に求人票を閲覧し、応募について相談しながら進めることが重要です。
2.求人票を閲覧する際の注意点
どのような方法で求人票を探すにしても、以下の点に注意しながら活動を進めましょう。
- ・複数の情報源を確認:一つの方法に固執せず、複数の方法を組み合わせて情報収集を行うことで、より多くの選択肢の中から自分に合った企業を見つけることができます。
- ・情報の整理:気になる求人票は、会社名・職種・勤務地・給与・応募期間などをメモに残したり、スマートフォンで写真やスクリーンショットを撮ったりして、後から見返せるように整理しておきましょう。
- ・疑問点は積極的に質問:少しでも不明な点や不安な点があれば、学校の先生や、可能であれば企業の人事や採用担当者に遠慮なく質問し、疑問を解消しておくことが大切です。
- ・応募期間の厳守:高校生の就職活動は、情報解禁日や応募期間が厳しく定められています。スケジュールをしっかり把握・管理し、遅れないように注意しましょう。
3.まとめ
|
方法 |
向いている人 |
メリット |
デメリット |
|
① 学校に届いた求人票 |
地元就職/学校推薦を活かしたい人 |
学校が内容確認済で安心/推薦が有利/先生のサポートが手厚い |
求人数が限定的/複数応募できない制約も |
|
② 求人サイト |
幅広く求人を見たい/ネットに慣れている人 |
全国の求人が検索可能/24時間アクセス/企業比較が簡単 |
情報の真偽確認が必要/サポートが薄く自己責任の部分が大きい |
|
③ ハローワーク(学校経由) |
学校やサイトで見つからなかった人/地域密着型を希望する人 |
学校に来ない求人にも出会える/地元企業の情報が豊富 |
個人では応募不可/先生を介して応募する必要がある |
|
④ 高卒就職情報WEB提供サービス |
国のサービスで信頼性ある情報を得たい人/全国規模で探したい人 |
全国の求人にアクセス可/印刷も便利/公的サービスで安心 |
学校発行のIDが必要/個人で自由閲覧できない |
高校生の就職活動において、求人票を見つける方法は多岐にわたります。
最も基本的な「学校に届く求人票」の活用に加え、情報量豊富な「求人サイト」の利用、そして「ハローワーク」や「高卒就職情報WEB提供サービス」といった公共機関の支援を活用することができます。
どの方法を選ぶにしても、積極的に情報収集を行い、疑問点を解決する姿勢が重要です。
特に進路指導の先生との密な連携は、高校生の皆さんの就職活動を成功させるための重要な鍵となります。
焦らず、自分に合った求人票を見つけるために、粘り強く活動を続けてください。高校生のための就活サイト「ジョブドラフト」では、皆さんの輝かしい未来を応援しています!